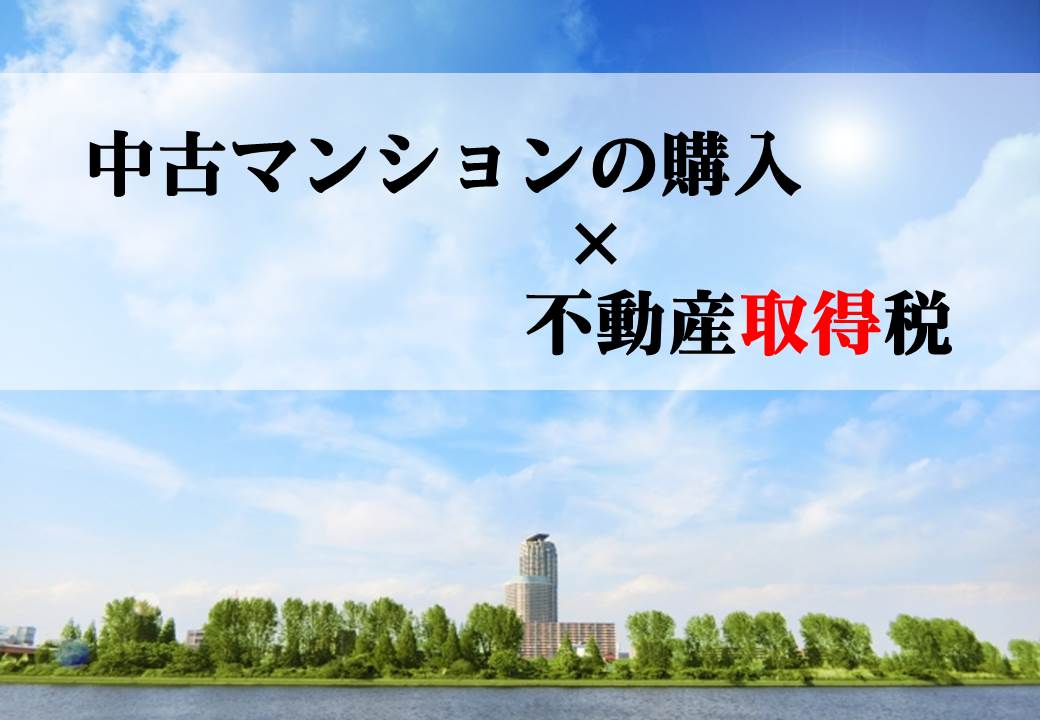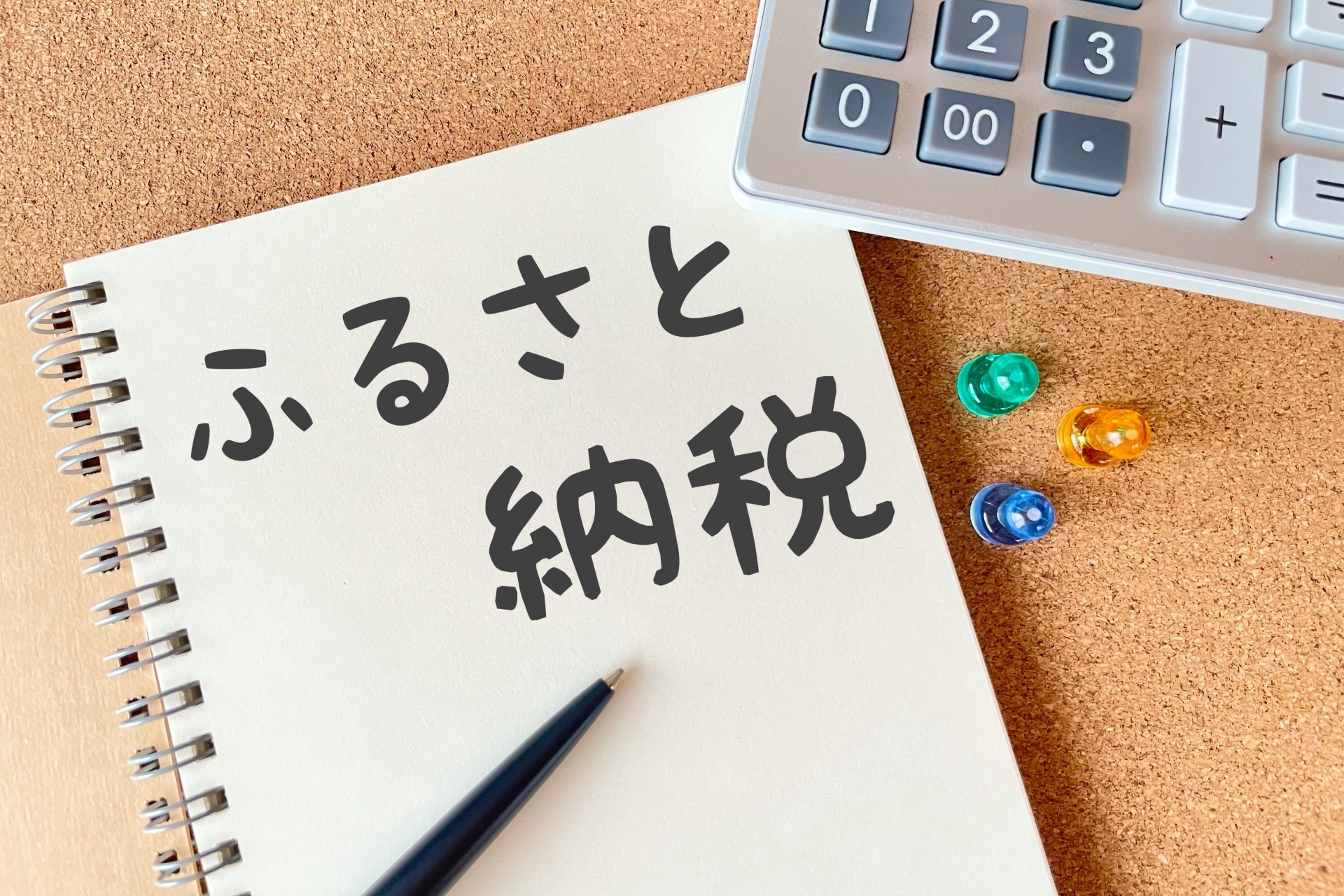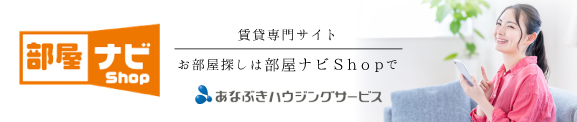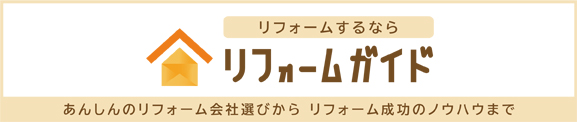みなさんこんにちは!
今回は銀行に預けたお金の利子にかかる税金です。
預貯金にかかわる税金とは?
もともと預けたお金についた利子部分が課税対象になります。
利子部分が「利益」とみなされるのですね。
仮に利率を0.125%とすると・・・
100万円(預けたお金) ×利率 0.125% = 1,250円(利子)
この「利益」にあたる部分を「利子所得」と言います。
これは、所得のひとつで預貯金だけでなく、その他に公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得も含まれます。
*合同運用信託・・・金銭を信託財産として信託銀行などに預け、運用方法が同じ人と合同で運用されて出た収益が信託金額に応じて支払われる商品
*公社債投資信託・・・株式を入れず国際や金融債など安全性の高い公社債を中心に運用する投資信託
*公募公社債等運用投資信託・・・公社債投資信託のうち不特定かつ多数(50名以上)の投資家に向けて募集する投資信託
この利子所得が課税対象となり、国税と地方税が取られています。
税率は?
所得税(国税)部分の税率は一律 15.315% です。 所得税の金額のうち復興税が2.1%となっています。
その他に地方税 5% が課税されています。
上の例では所得税187円、復興税4円、地方税 62円となります。
所得税 1,250円(利息)× 15.315%=191円
復興税 191円×2.1%=4円
→ 所得税 187円 復興税 4円
地方税 1,250円(利息)×5% =62円
源泉徴収額 =187円 + 4円 + 62円 =253円
税金控除後の金額 1,000,000(元金) + 1,250円(利子)- 191円(国税)- 62円(地方税)= 1,000,997円 (通帳記帳額)
非課税になるものはあるの?
「マル優」
国内に居住する個人で障害者手帳をお持ちの方は最初に預け入れる日までに「非課税貯蓄申告書」を金融機関の営業所を通じて税務署長に提出し、預入の都度「非課税貯蓄申込書」を提出した場合は、一人350万円までの利子について非課税扱いとして預け入れができます。
350万円という金額は金融機関ごとではなく、預け入れる金融機関以外にも非課税貯蓄申告書を提出している場合は、その金額を差し引いて申告することになります。
この制度は通称で「障害者等のマル優」と言われています。
「障害者等の特別マル優」は購入する対象が国債や地方債の場合を言います。上記とは別枠で350万円までの利子について非課税となります。
このマル優制度は2021年から遺族年金を受けている妻・寡婦年金や母子年金を受けている人もマル優や特別マル優を利用することができるように変更されました。
郵便貯金の非課税制度は郵政民営化の時(2007年10/1)に廃止されましたが、施行日前に預入をしていたものの利子については満期・解約までの間、引き続き非課税となります。
「財形貯蓄制度」
55歳未満の従業員が会社を通じて5年以上の期間にわたって給与天引きで積み立てる*財形住宅貯蓄と*財形年金貯蓄は合わせて元利合計550万円までは利子所得に税金がかかりません。
ただし、財形年金貯蓄だけの場合で、保険型商品で運用する場合は385万円までとなります。
*財形住宅貯蓄は持ち家の取得や増改築を目的とした貯蓄
*財形年金貯蓄は60歳以降に年金として5年以上の期間にわたって受け取るための貯蓄
「納税準備預金」
納税するための口座である納税準備預金も非課税となります。
納税準備預金は個人でも法人でも開設することができ、金融機関によっては普通預金の金利よりも高く設定しているところもあるようです。
他の預金と区分して管理されていることが必要で、納税以外の目的で利用すると所得税がかかります。
非課税所得ー国税庁HPより
マル優制度・その他全ての場合で外貨建ての貯蓄は対象外です。
また、法人口座の利子に対する地方税は2016年から廃止となり、国税のみとなりました。
法人では、利益に対して法人税がかかるわけですが、この利子に対する所得税・復興税は法人税の前払いという扱いになり、二重払いを防ぐ形になっています。
納税方法は?源泉分離課税制度って何?
預金通帳では税金が引かれた後の手取り額が記帳されていますよね。
預貯金の利息は源泉分離課税制度がとられているため、個人が納付する必要はありません。
源泉分離課税制度は、納付した個人が直接納付するのではなく、金融機関や会社など特別徴収者が個人に代わって納付する方法です。
預貯金の税金は利息を支払った時に金融機関が徴収し、翌月10日までに申告・納入することになっています。
国税は国に対して納付し、地方税は都道府県へ納付することになるのですが、預貯金に関わる地方税は現在、口座を持っている人の住所地への納付ではなく、金融機関の本社・営業所等の所在地へ納付される仕組みとなっています。このため、地方税の収入が大都市に多く分配され偏りが見られるため、是正しようという動きがあるようです。
復興税のつかいみち
2013年から課税されることになった復興税ですが、2025年度は以下の予算が立てられました。
被災者支援、住宅再建復興まちづくり、産業・生業の再生、原子力災害からの復興再生、創造的復興などに使われています。
おわりに
利子所得について調べていると「こども銀行」というのがあったことを知りました。
こどもが金融機関の助けを得ながら自主的に窓口や帳簿などの業務をする銀行で、利子については非課税でした。戦後に設立が始まり、1955年頃をピークに数が減り、2001年廃止となったようです。
大人が見守る中でのこどもの社会勉強のひとつだったんでしょうね。
戦後の厳しい社会情勢を想像しながらも、ちょっとあたたかい気持ちになりました。
田中 智恵
財務・経理本部 経理課
田中 智恵(たなか ちえ)
2009年入社
2年程組合の庶務業務を経た後、会社の経理業務に携わってきました。
現在は、九州エリアの経理を担当。
主に預金関係、売上・原価のチェック、立替精算書チェック、問い合わせ対応を行っています。
趣味:庭の手入れ、音楽鑑賞、読書
資格:日商簿記二級・管理業務主任者・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士ほか
最新記事 by 田中 智恵 (すべて見る)
- 個人が輸入する時にかかわる税~その② - 2025年7月10日
- 個人が輸入する時にかかわる税~その① - 2025年6月10日
- 預貯金の利子にかかわる税金 - 2025年5月10日