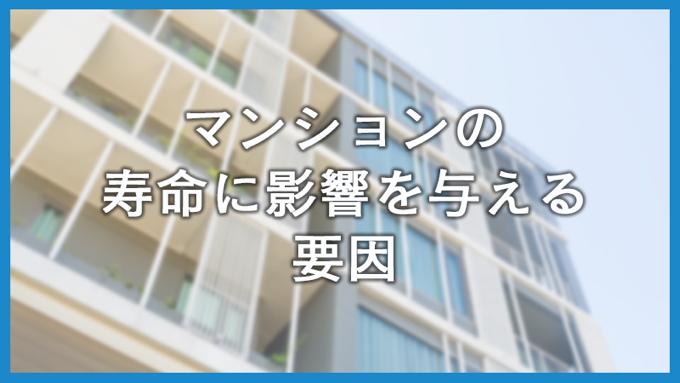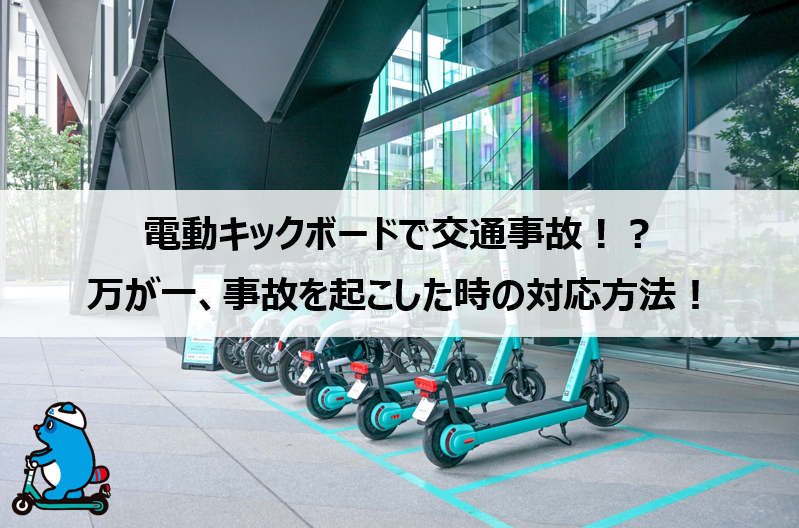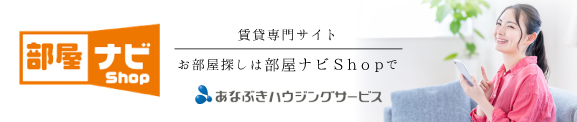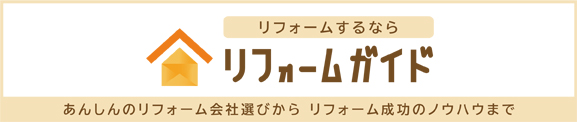形あるものには寿命がありますが、マンションも例外ではありません。マンションの寿命は、建物の構造や立地環境などによって異なります。長期的に暮らすには、どの程度で寿命が来るか把握することが大切です。
本記事では、マンションの寿命について、影響を与える要因や確認すべき項目を解説します。あわせて、長持ちさせるためのポイントも解説するためぜひ最後までご覧ください。
マンションの寿命とは
マンションを管理し、長期的に資産を維持するうえで寿命の拍は不可欠です。まずは、マンションの平均寿命について解説します。
出典:国土交通省「期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値向上について」(https://www.mlit.go.jp/common/001011879.pdf)
寿命目安は約70年
国土交通省の資料によると、一般的なRC造(鉄筋コンクリート造)のマンションにおける平均寿命は68年という結果が出ています。
これは、固定資産台帳の滅失データを踏まえて「区間残存率推計法」で算出されています。区間残存率推計法とは、特定の期間内にどれだけの割合の建物が残存しているかを分析する手法です。
ただし、あくまでも建物自体の平均的な耐久年数であり、メンテナンスや修繕次第で寿命は変動します。定期的に適切なメンテナンスを行えば、平均寿命より長く維持することも可能です。一方で、維持管理を怠れば、一般的な平均寿命より早く老朽化が進む可能性もあります。
100年以上もつ場合もあります
マンションは、適切な管理と修繕によって100年以上の寿命を保つことが可能です。高度経済成長の只中にあった1970年代は、マンションラッシュと呼ばれ、大量に建設されました。こうした影響もあり、近年は築年数の長いマンションが増えているのが現状です。ストックマンションが増加するなかで、国土交通省ではマンションの長寿命化を推奨しています。
その理由として、日頃の適正な管理と計画的な修繕によって、建物の耐久性が維持できる点があげられます。
とくに、外壁の補修や給排水管の交換、屋上防水の更新といった適切な大規模修繕は、建物の老朽化を遅らせるポイントのひとつです。また、安全性を向上させる耐震補強も、長寿命化の重要な要素といえるでしょう。
実際に、適切な維持管理を行っているマンションは、築年数が経過した現在でも十分の機能を維持しています。
法廷耐用年数とマンション寿命の違い
マンションには「法定耐用年数」と「寿命」があり、この2つは異なる概念です。法定耐用年数は、国税庁によって定められた税法上の減価償却期間を指します。
建物の種類ごとに異なり、実際の建物の使用可能な期間を意味するものではありません。
たとえば、RC造やSRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)のマンションは47年とされており、以降は建物の価値がなくなります。
一方で、前述したようにマンションの実際の平均寿命は68年です。また、適切な維持管理や修繕を行えば、100年以上使用できる場合もあります。例えば、外壁の補修や給排水管の交換、屋上防水の更新を適切な時期に行うことで、建物の機能をながく維持することが可能です。
このように、法廷耐用年数はあくまで財務上の基準であり、マンションの寿命を判断する際には、建物の管理状況や修繕履歴を確認する必要があります。
出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf)
マンションの寿命に影響を与える要因
マンションの寿命は構造や材質、立地環境、メンテナンス状況などに影響されます。ここでは、マンションの寿命に影響を与える要因を解説します。
建物の構造と材質
マンションの寿命は、建物の構造と使用される材質によって大きく左右されます。RC造やSRC造の建物は、鉄筋とコンクリートの組み合わせにより強度が高く、耐震性や耐火性に優れている点が特徴です。
適切な維持管理ができれば、100年以上使用できるケースも少なくありません。一方で鉄骨造(S造)や木造の建物は、耐久性が低いため、寿命も比較的短くなります。
たとえば、同じ築年数のマンションでもSRC造の建物は構造が強固であり、大規模修繕を適切に行えば50年以上使用できる可能性が高まります。
対照的に、S造のマンションでは経年劣化が進みやすく、早期の補修が求められるケースが多いです。また、コンクリートの質や鉄筋の防錆処理の有無も、耐久性に影響を与えます。
このように、マンションの構造と材質は、その寿命を決定する重要な要素です。耐久性の高い建材と適切なメンテナンスを組み合わせることで、マンションの長寿命化が可能になります。
立地環境
マンションの寿命には、立地環境も影響します。特に建物の耐久性を左右する要素が、地盤の強さや気候条件です。
地盤が弱い地域では建物の沈下や傾きが発生しやすく、湿気の多い場所ではコンクリートの劣化が早まりやすくなります。また、沿岸部では塩害によって鉄筋がさびるため、寿命が短くなる傾向にあります。
加えて、地震や洪水のリスクが高い地域では、構造へのダメージが蓄積され、寿命が短くなる可能性があるでしょう。たとえば、液状化のリスクが高い埋め立て地や軟弱地盤のエリアでは、建物が不均等に沈下することがあります。
一方で、岩盤のうえに建つマンションは地盤が安定しているため、長期間の維持が期待できます。とくに、新耐震基準を満たしているマンションは、地震の揺れに対する耐性が高く、寿命を延ばしやすいでしょう。
このように、マンションの購入や維持管理の際には立地の特性を考慮し、災害対策や適切な修繕計画を立てる必要があります。
維持管理と修繕状況
マンションの寿命を延ばすためには、適切な維持管理と計画的な修繕が不可欠です。管理が行き届いているマンションは老朽化の進行を抑え、長期間にわたって快適な住環境を維持できます。
実際、長寿命化を目指すマンションでは、12年〜15年ごとに大規模修繕を行うケースが一般的です。また、適正な管理体制が整っているマンションは、築年数が経過しても価値を維持しやすく、売却時の市場評価も高くなる傾向があります。
このように、マンションの寿命は、維持管理や修繕の質によって大きく変わります。
耐震性能
耐震基準も建物の寿命を判断するポイントです。耐震基準は、1981年5月以前の建物に適用される「旧耐震基準」 と1981年6月1日以降に、建築確認申請が提出された建築物を対象にした「新耐震基準」の2つに分けられます。
新耐震基準を満たすマンションは、震度6強〜7程度の地震でも倒れないように建設される一方で、旧耐震基準では中規模地震(震度5程度)で建物の機能を維持する点が特徴です。
たとえば、同じ築年数のマンションでも、新耐震基準を満たすRC造であれば耐久性が高く長期間使用できる可能性が高いでしょう。さらに、耐震補強をしているマンションは、より長い寿命が期待できます。
マンションの寿命を知るために確認すべき項目
マンションの寿命は、構造や立地条件、メンテナンスの有無などによってさまざまです。ここでは、マンションの寿命目安を知るために確認しておきたい項目を3つ解説します。
築年数と構造の確認
マンションの寿命を判断する際は、築年数と構造の確認が重要です。一般的に、築年数が浅いマンションほど耐久性が高いといえます。とくに、1981年6月以降に建築されたマンションは、新建築基準法が適用されているため、より強度が高いです。
また、マンションの構造も重要な要素です。RC造やSRC造の場合、耐久性が高いため、適切なメンテナンスを行えば、長寿命を期待できます。
一方、木造や軽量鉄骨造の場合、耐久性が低く、築年数が進むにつれて劣化が早く進行することがあります。
過去の修繕履歴と修繕計画
過去の修繕履歴と将来的な修繕計画の確認も、マンションの寿命を判断するポイントです。適切な修繕が実施されているマンションは老朽化を防ぎ、長く住み続けられます。建物の経年劣化を遅らせるには、定期的な修繕が欠かせません。
とくに、築30年以上のマンションの場合は、12〜15年ごとに大規模修繕が実施されているか確認しましょう。また、修繕積立金が適正に確保されていることや、将来の費用計画が立てられていることなども、マンションの寿命を左右します。
外壁、屋上、給排水管などの劣化状況
マンションの寿命を判断する際には、外壁、屋上、給排水管の劣化状況も確認しましょう。これらの部位が劣化すると、建物全体の耐久性が低下します。
たとえば、外壁のひび割れや剥離は、雨水の浸入につながり、コンクリートの劣化や鉄筋の腐食につながりかねません。また、屋上の防水機能の低下は、雨漏りを引き起こします。
外壁補修や防水工事、給排水管の更新が行われていない場合、パーツだけの劣化だけでなく、建物全体の寿命が大幅に短縮する可能性があるため注意しましょう。
マンションが寿命を迎えたときの選択肢
マンションが寿命を迎えた場合は、建て替えや売却など多様な選択肢があります。ここでは、3つの選択肢を解説します。
立て替え
マンションの寿命が近づいた際、建て替えは選択肢のひとつです。老朽化が進み、耐震性や居住環境に問題がある場合、建て替えによって安全で快適な住まいを確保できます。
その理由は、築年数が経過すると修繕では対応できない劣化が進み、設備の更新にも限界があるためです。また、旧耐震基準のマンションは耐震補強が難しく、災害時のリスクが高まります。
ただし、建て替えには合意形成が必要で、住民の5分の4以上の賛成が求められます。取り壊しや新築には高額な費用がかかるため、売却して建て替え資金を捻出するケースも考えられるでしょう。そのほか、建物の解体費用や仮住まいの手配など、居住者の負担が発生する点も考慮する必要があります。
このように、マンションの建て替えは資金や合意形成が課題となりますが、安全で資産価値の高い住環境を得るための有効な手段です。
売却
マンションが寿命を迎えた際は、売却もひとつの手段です。より良い条件で売却するには、修繕費用の増加や老朽化により資産価値が低下する前に検討する必要があります。売却方法として、デベロッパーに売却する方法と更地にして売却する方法の2種類が挙げられます。
デベロッパーへの売却では、マンションの建て替えを前提とした買取が行われるケースが一般的です。資産価値を引き出すのに有効であり、古いマンションに適しています。ただし、デベロッパーに売却する場合、売却代金から解体費用が差し引かれます。
一方、更地にして売却する場合、建物を解体する費用がかかるものの、用途の自由度が高く、土地の価値に応じた売却が可能です。
マンションの売却には方法ごとのメリット・デメリットを理解し、適切なタイミングで判断することが重要です。
放置される場合もある
マンションが寿命を迎えても建て替えや売却、解体といった決定がされず、放置された状態で住民が暮らし続けるケースがあります。これは、住民間での合意形成が難しい場合や、経済的な理由で対策を講じられない場合に多い事例です。
その理由として、建て替えには住民の5分の4以上の同意が必要であり、売却や解体にも高額な費用がかかる点が挙げられます。
とくに、住民の高齢化が進んだマンションでは、意向がまとまりにくいほか、修繕費の負担も困難です。また、所有者不明の区分が増えると、管理が行き届かなくなります。
寿命を迎えたマンションが放置されると、安全性が低下し、住環境が悪化します。早めに対策を検討し、適切な管理や売却を進めることが、資産価値を維持するために重要なポイントです。
マンションの寿命を延ばすための対策
マンションを長く維持管理するには、適切な対策を講じることが大切です。ここでは、マンションの寿命を延ばすための対策を3つ解説します。
適切なメンテナンスと修繕
マンションの寿命を延ばすには、定期的なメンテナンスと計画的な修繕が欠かせません。早めの対応を行うことで、建物の劣化を防ぎ、長期間にわたって安全な住環境を維持できます。
たとえば、設備や外壁の劣化を放置すると修繕費が増大し、建物全体の耐久性低下を招きます。また、外壁のひび割れやタイルの剥離なども安全性につながるため、早期補修が不可欠です。
加えて、12〜15年ごとに大規模修繕を実施して、外壁補修や設備の更新が推奨されます。これにより、建物の老朽化を抑え、修繕費の急増を防ぐことが可能です。このように、早めの点検と適切な修繕により、住環境を守りながら資産価値を維持しやすくなります。
管理組合の役割と活動
マンションの寿命を延ばし、資産価値を維持するためには、管理組合の適切な運営が不可欠です。どのような建物でも、時間の経過にともなう劣化は避けられません。
そのため、計画的な修繕を行う必要があります。管理組合は、長期修繕計画の見直しや修繕積立金の適正な管理において重要な役割を果たす組織です。
たとえば、12〜15年ごとの大規模修繕を計画し、外壁や給排水設備の修繕費を事前に積み立てれば、急な費用負担を回避できます。一方で、修繕積立金が不足すると、住民の追加負担が発生しトラブルになりかねないほか、修繕が遅れるリスクも考えられるでしょう。
このように、管理組合が正しく機能しているマンションは、修繕計画の実行がスムーズになり、安全で快適な住環境を維持できます。
耐震補強やバリアフリー化
耐震補強やバリアフリー化の対策も、マンションの寿命を延ばすポイントです。旧耐震基準で建てられたマンションは、耐震性が低く、大地震発生時に倒壊のリスクがあります。寿命を延ばすためには耐震診断を行ったうえで、耐震補強工事を実施しなければなりません。
また、エレベーターがない物件や段差の多い共用部は、高齢者にとって負担であり、住み続けることが困難です。こうした課題を解決するには、手すりやスロープの設置が必要です。
高齢者を含む誰もが将来にわたって安心して暮らせる住環境を維持するためにも、耐震補強とバリアフリー化の計画的な実施が求められます。
まとめ
今回は、マンションの寿命と資産価値を守るためのポイントを解説しました。マンションは、メンテナンスや修繕を定期的に行うことで、寿命を延ばせる可能性があります。
とくに、12〜15年に一度の大規模修繕は欠かせません。外壁や屋上、給排水管の修繕を実施して、建物の老朽化を回避しましょう。
あなぶきハウジングサービスは、24時間365日体制で迅速に対応できる、自社運営のコールセンターを設置しています。万全のサポート体制と確かな専門性で、これからも安心・快適な暮らしを支えてまいります。マンション管理に関するお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
あなぶきハウジンググループ公式
あなぶきハウジンググループは、これからの時代を創造するため
グループ全体で企業価値の向上を行っています。
最新記事 by あなぶきハウジンググループ公式 (すべて見る)
- ランサムウェア被害発生のお知らせ(第1報) - 2026年2月3日
- マンションの修繕積立金の値上げは本当に必要?修繕積立金の重要性とは - 2026年1月5日
- マンション管理会社は変更できる!失敗しないための手順と注意点 - 2025年12月29日